いま一度よく耳にする「マイコプラズマ」と、その代表的な感染症「マイコプラズマ肺炎」について、仕組み・症状・検査・治療・予防までをまとめました。専門用語はできるだけかみくだいて説明します。
1) マイコプラズマとは?
- 細菌の一種ですが、細胞壁を持たないのが最大の特徴。
→ そのため、ペニシリンなど“細胞壁を壊す”タイプの抗菌薬は効きにくい(無効)。代わりにマクロライド系などが用いられます。 (疾病管理予防センター) - 呼吸器に感染する種類が有名で、特に Mycoplasma pneumoniae(肺炎マイコプラズマ) が問題になります。 (疾病管理予防センター)
2) マイコプラズマ肺炎ってどんな病気?
主な症状
- 発熱、長引く乾いた咳、だるさ、頭痛、のどの痛み など。
多くは風邪に似た“ゆっくり始まる”経過で、咳がしつこく続くのが特徴です。 (疾病管理予防センター)
だれに多い?
- 学童~若年層で多くみられ、学校や職場など人が集まる環境で広がりやすい感染症です。 (疾病管理予防センター)
うつる経路と潜伏期間
- 咳やくしゃみの飛沫で広がります。
- 潜伏期間はおよそ2–3週間(1–4週間のことも)。発症前から周囲に広げてしまうことがあります。 (疾病管理予防センター)
3) 検査と診断
- 症状や胸部X線などに加え、咽頭ぬぐい液の遺伝子検査(PCR)、抗原検査、血清(抗体)検査を組み合わせて診断します。培養は可能ですが時間がかかります。 (国立健康危機管理研究機構)
4) 治療の考え方
- 原則として抗菌薬治療を行います。第一選択はマクロライド系(例:アジスロマイシン等)。
マクロライドが効きにくい場合や年齢によってはテトラサイクリン系やフルオロキノロン系を検討します(小児では年齢制限に注意)。 (厚生労働省) - マクロライド耐性株(MRMP)は日本の小児領域で高率に報告された時期があり、地域や年で差はあるものの、臨床上の留意点です。 (Frontiers)
参考:2024年には各国で感染増加が観察された報告があり、季節性や周期性に加えてパンデミック後の流行動態の変化が示唆されています。受診地域の最新情報は公的機関の発表もご確認ください。 (疾病管理予防センター)
5) 予防のポイント(ワクチンはある?)
- 手洗い、咳エチケット(マスク)、体調不良時は無理をしないといった基本対策が有効。
- 承認されたワクチンはありません。学校・職場では飛沫・接触予防策が推奨されます。 (国立健康危機管理研究機構)
6) 早見表(要点まとめ)
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 原因菌 | Mycoplasma pneumoniae(細胞壁がない) |
| 主症状 | 発熱、長引く乾いた咳、だるさ、頭痛 など |
| 好発 | 学童~若年層、集団生活で拡大しやすい |
| 潜伏期間 | 2–3週間(1–4週間ことも) |
| うつり方 | 飛沫(咳・くしゃみ)、近距離接触 |
| 検査 | PCR/抗原/抗体検査+画像所見など |
| 治療 | マクロライド系中心(耐性なら他系統を検討) |
| 予防 | 手洗い・咳エチケット・体調管理(ワクチンなし) |
(根拠:CDC・厚労省・国立感染症研究所 ほか) (疾病管理予防センター)
7) 受診の目安
- 高熱が続く/咳が長引く(1週間以上)/息苦しさや胸痛がある
- 子どもや高齢者、基礎疾患のある方で体調が悪い
こうした場合は早めに医療機関へ。自己判断で市販薬のみで長期対応するのは避けましょう。 (疾病管理予防センター)
8) 制度面(日本)
- マイコプラズマ肺炎は感染症法の五類・定点把握の対象。学校保健安全法では条件により第三種の「その他の感染症」として扱われます。登校・出勤は全身状態や咳の程度、医師の判断に従いましょう。 (国立健康危機管理研究機構)
最後に
本記事は公的機関や学術情報に基づく一般解説です。個別の症状や治療は必ず医療機関でご相談ください。
参考文献(抜粋):CDC(Clinical Overview / Causes / Clinical Features / Surveillance)、厚生労働省、国立感染症研究所、国立成育医療研究センター、学術レビュー(Frontiers in Microbiology ほか)。 (疾病管理予防センター)
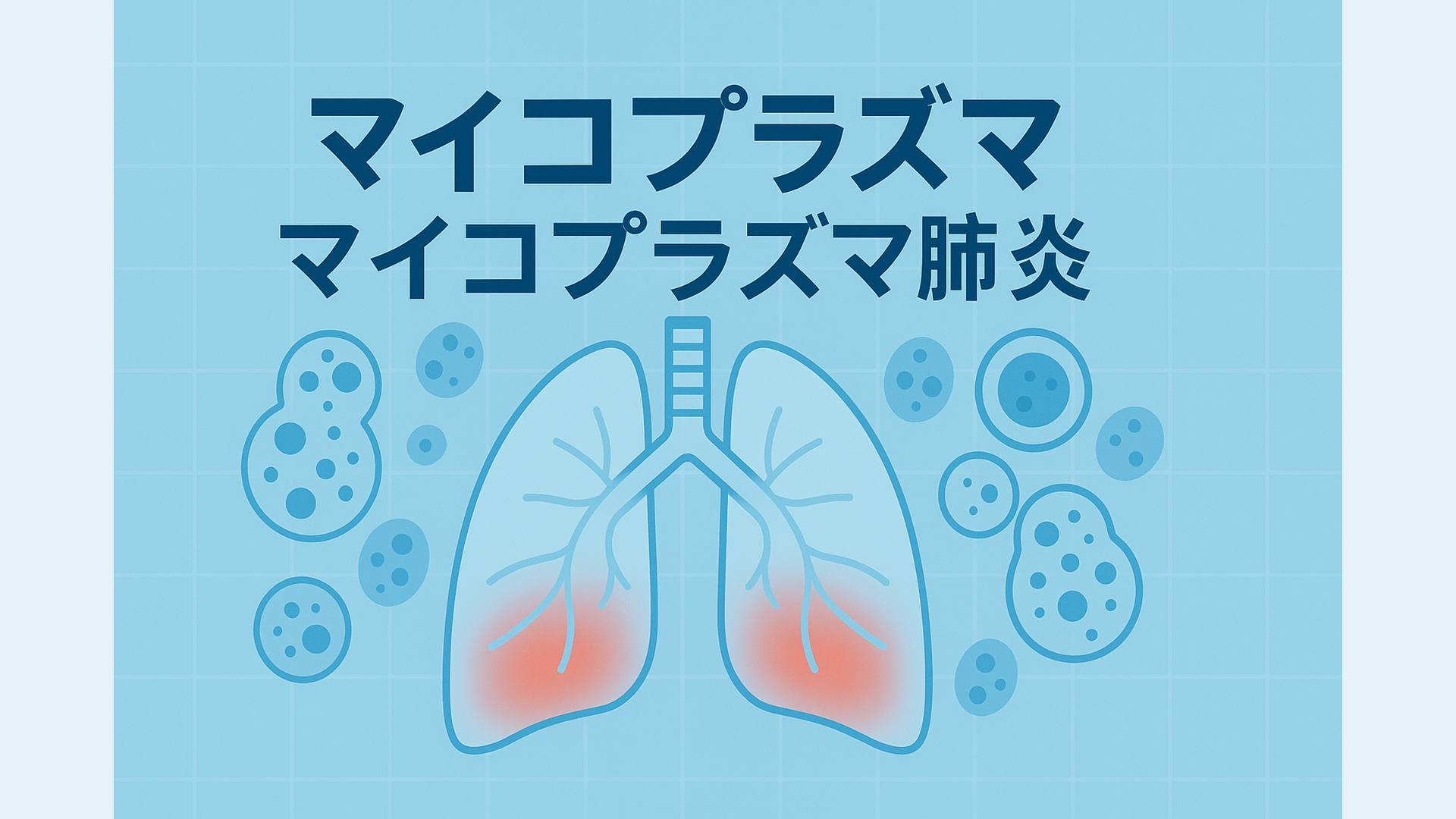

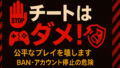
コメント