小学2年生になると、いよいよ「掛け算(かけざん)」と「九九(くく)」を習います。
でも最初は「かけるって何?」「どうして覚えなきゃいけないの?」と、子どもたちはピンとこないものです。
ここでは、子どもが楽しく理解できるように、掛け算と九九の教え方をわかりやすくまとめました。
1. 掛け算は「同じ数をくり返し足す」こと
まずは「掛け算ってなに?」という部分から説明しましょう。
たとえば、お皿にりんごが2個ずつのっています。
お皿が3つあると、りんごはぜんぶでいくつでしょう?
2+2+2=6
この「2を3回たした」計算を、短く書けるようにしたのが掛け算です。
つまり、
2×3=6(にさんがろく)
ということになります。
子どもにはこう伝えるといいでしょう。
「掛け算は、同じ数を何回も足すときの便利な言い方なんだよ。」
2. 九九は「掛け算の結果を覚えやすくした歌」
掛け算の意味がわかったら、次は「九九(くく)」です。
九九は、掛け算の答えをリズムで覚える歌のようなものです。
にいちがに
ににんがし
にさんがろく
にしがはち…
と、くり返し声に出して覚えます。
リズムで覚えると、頭の中で「同じ数をくり返す」イメージが自然に身につきます。
3. 生活の中で「掛け算」を感じさせよう
いきなり九九を覚えるより、身近な例で「掛け算って便利!」と感じさせることが大切です。
- 2個入りのお菓子を3袋買ったら、ぜんぶで6個。
- 椅子が4本足で、3脚あると足は12本。
- 5円玉を4枚で20円。
こうした体験を通して、
「2×3=6は、お菓子3袋分のことだね!」
と実感できるようになります。
4. 覚えやすい段から始めよう
九九は一気に覚えようとせず、「わかりやすい段」から進めましょう。
| 段 | 特徴 | 例 |
|---|---|---|
| 2の段 | 数が2ずつ増える | 2, 4, 6, 8… |
| 5の段 | 時計やお金と同じ間隔 | 5, 10, 15, 20… |
| 1の段・10の段 | 簡単で自信がつく | なんでもそのまま / 最後が0 |
まず「できた!」という成功体験を増やすことが大切です。
5. 九九を楽しく覚える工夫
九九は「暗記」が中心ですが、楽しさを取り入れると覚えやすくなります。
- 九九カードやアプリで遊ぶ
- 親子でクイズ形式にする
- 九九の歌をかけて一緒に口ずさむ
- 正解したらシールを貼るなど、ごほうび方式にする
学びの時間を「楽しい時間」に変えることで、自然と身につきます。
6. 覚えることより「使えること」が大切
九九を全部覚えても、それを使えなければ意味がありません。
日常の中で声をかけてみましょう。
「おにぎりを2こずつ3人分作るといくつ?」
「5円玉が6枚あると、いくらになる?」
こうしたやりとりを重ねることで、九九が「生活で使える算数」になります。
まとめ
掛け算は、同じ数をくり返し足すときの便利な数のしくみ。
九九は、その結果をリズムで覚えやすくした表です。
子どもが「意味」と「楽しさ」を感じながら覚えると、
ただの暗記ではなく、一生使える“数の感覚”が育ちます。

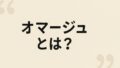
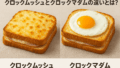
コメント