シーサーの起源
シーサーは、沖縄を代表する伝統的な守り神の像です。ライオンのような姿をしており、屋根や門に置かれて家や人々を悪霊から守る役割を担ってきました。
その起源は中国から伝わった獅子像にあり、琉球王国の時代に沖縄独自の文化として発展しました。「獅子(しし)」が沖縄の方言で「シーサー」と呼ばれるようになったのが名前の由来です。
口の開け閉めに込められた意味
シーサーは一対で置かれることが多く、それぞれの口の形に意味が込められています。
- 口を開けたシーサー:邪気を追い払う
- 口を閉じたシーサー:福を招き入れて守る
この組み合わせによって、「悪いものを退け、良いものを取り込む」と考えられてきました。
現代に息づくシーサー
昔は赤瓦の屋根の上に設置されていましたが、今では玄関や庭、商店の入り口などにも広く飾られています。観光客向けのお土産としても人気があり、陶器や石像のほか、かわいらしいキャラクター風のデザインも登場しています。
まとめ
シーサーは、沖縄の人々の生活に根付いた守り神として、今も親しまれ続けています。旅行で沖縄を訪れた際には、街角や屋根の上にあるシーサーにぜひ注目してみてください。きっと地域の文化や歴史をより身近に感じられるはずです。


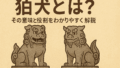
コメント