こんにちは!
今日は分数の計算でとっても大事な「通分(つうぶん)」と「帯分数(たいぶんすう)」について、わかりやすく説明します。
これがわかると、分数のたし算やひき算がスイスイできるようになりますよ!
■ 通分(つうぶん)とは?
通分とは、分母(ぶんぼ)を同じ数にそろえることです。
分母がちがうままだと、分数どうしをたしたりひいたりできません。
◎ 例:1/2 + 1/3 のとき
分母が 2 と 3 でちがうから、そのままでは計算できません。
そこで、2と3の両方で割り切れる数(最小公倍数)をさがします。
2と3の最小公倍数は 6 です。
だから、分母を6にそろえましょう。
1/2 = 3/6
1/3 = 2/6分母がそろったら、分子をたします。
3/6 + 2/6 = 5/6これで通分ができました!
◎ 通分のやり方まとめ
- 分母どうしの 最小公倍数 を見つける
- 分母をその数にそろえる(分子にも同じ数をかける)
- 分母が同じになったら、分子をたす・ひく!
■ 帯分数(たいぶんすう)とは?
帯分数とは、整数と分数がいっしょになった数のことです。
たとえば:
1 1/2, 3 2/5のように書きます。
読み方は「1と2分の1」「3と5分の2」など。
帯(おび)のように数字がつながっているので「帯分数」といいます。
◎ どういう意味?
「1と2分の1」は、実は 1 + 1/2 のこと。
つまり、1と半分を合わせた数なんです。
1 1/2 = 3/2◎ 仮分数との関係
分子が分母より大きい分数(例:3/2、7/4など)を 仮分数(かぶんすう) といいます。
帯分数と仮分数は、つぎのように変えられます。
| 変換のしかた | 例 |
|---|---|
| 帯分数 → 仮分数 | 2 3/4 = 11/4 (2×4+3) |
| 仮分数 → 帯分数 | 11/4 = 2 3/4 (11÷4=2あまり3) |
■ まとめ
| 言葉 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 通分 | 分母を同じにそろえること | 1/2+1/3=5/6 |
| 帯分数 | 整数+分数の形 | 1 1/2=3/2 |
| 仮分数 | 分子>分母の分数 | 3/2=1 1/2 |
■ おまけ:イメージで覚えよう!
ピザを思い出してみてください。
1枚のピザを2等分したら、それが「1/2」。
1枚半食べたら「1 1/2」。
つまり、帯分数は「1枚と半分食べた!」という感じなんです。
★ ポイント
- 通分は「同じ単位に合わせること」
- 帯分数は「整数+分数」の形
どちらも分数を正しく計算したり、わかりやすく書いたりするためのテクニックです!
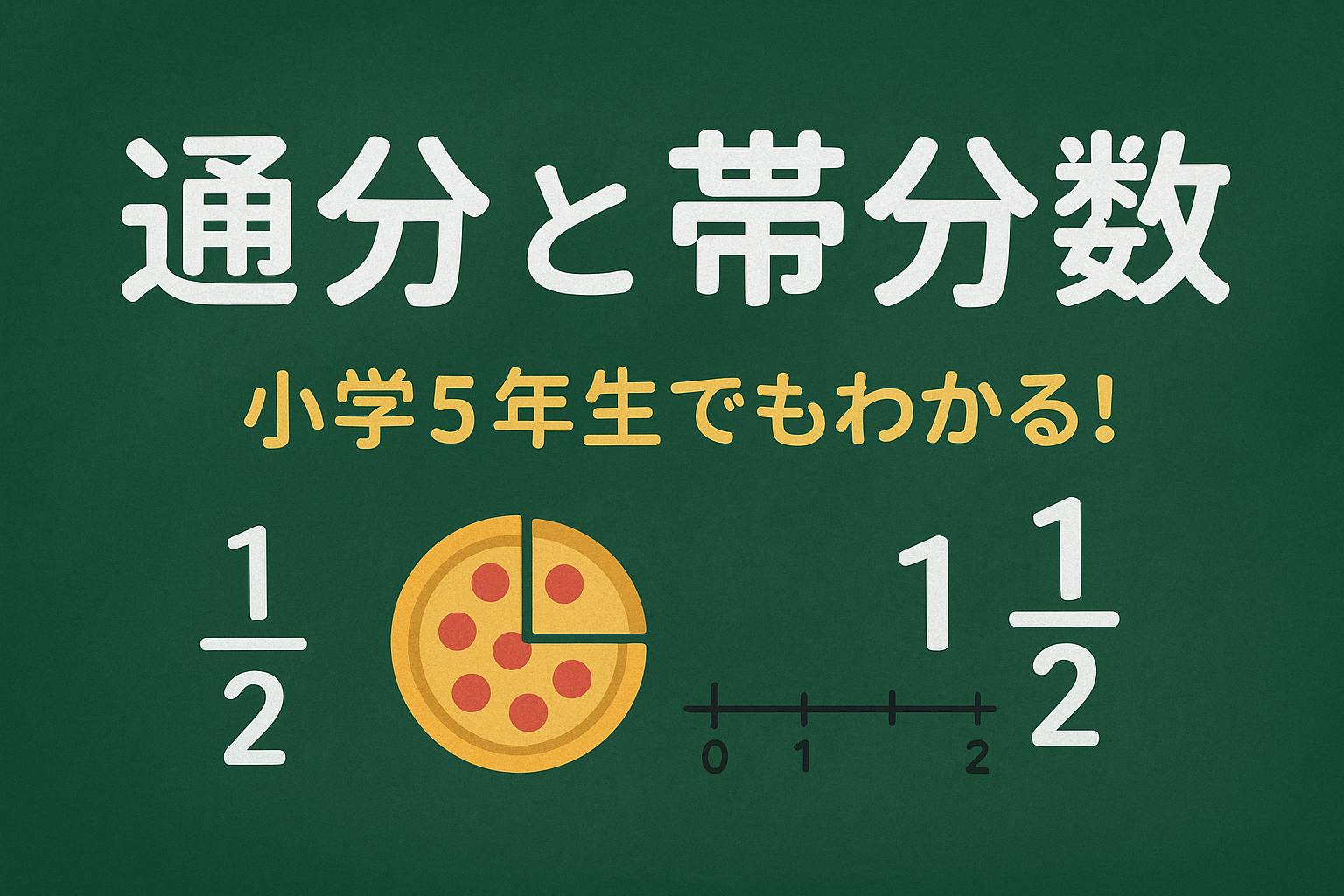
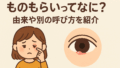
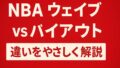
コメント