—マーケティング戦略の基礎を、実例と手順で整理—
この記事の要点
- レッドオーシャン:既存市場での競争優位がカギ(価格・機能・運用効率)
- ブルーオーシャン:価値軸を再設計して競争を無意味化、新需要を創出
- 小さく検証 → 当たり所を特定 → 拡張、の順で進めると失敗確率を下げられる
定義
- レッドオーシャン(Red Ocean)
既存の土俵で競合とシェアを奪い合う市場。価格競争・機能横並び・薄利化が起こりやすい。 - ブルーオーシャン(Blue Ocean)
顧客の「未満足」や非顧客の課題に着目し、別の価値軸で市場を再定義して新需要をつくる。
ざっくり比較
| 観点 | レッドオーシャン | ブルーオーシャン |
|---|---|---|
| 市場 | 既存・成熟 | 未開拓・再定義 |
| 競争 | 激しい/価格・機能で消耗 | 低い/競争そのものを外す |
| 武器 | コスト最適化、局所差別化、運用力 | 価値設計、体験デザイン、価格モデルの再発明 |
| 指標 | シェア、CPA/ROAS、回転率 | 新規需要、顧客生涯価値、プレミアム単価 |
| 主リスク | 薄利・模倣 | 需要不確実・検証外し |
レッド/ブルーを分ける“価値軸”
ブルーオーシャンは、同じカテゴリ内で「何を良くするか」の勝負をやめることが起点です。
例:ホテル
- レッド:同価格帯で部屋の広さ・朝食・立地を強化
- ブルー:「集中作業の場」×「仮眠」重視に再定義(静音・高速回線・椅子・防音・時間課金)
実務フレーム:ERRC(やめる・減らす・増やす・新設)
下の表を既存価値の棚卸しツールとして使います。
| やめる(Eliminate) | 減らす(Reduce) | 増やす(Raise) | 新設(Create) |
|---|---|---|---|
| 当たり前の付帯機能 | 過剰品質・過剰UI | 主要課題の解決度 | 新しい利用シーン/価格モデル |
例(SaaS)
- やめる:複雑な権限階層
- 減らす:個別カスタマイズ
- 増やす:初期設定ゼロ、既存ツール連携
- 新設:成果連動の料金、ワークフローの“前後工程”を代替する自動化
ブルーオーシャンの見つけ方(6ステップ)
- 非顧客の行動観察:使っていない/離脱した人は“なぜ”か
- 代替行動の洗い出し:顧客は今、何で済ませているか(Excel、外注、手作業など)
- ERRCで価値軸を再設計:やめる・減らす・増やす・新設
- 価格モデルの再発明:サブスク/従量/成果課金/バンドル・アンバンドル
- 小さく検証(MVP):
- スモークテスト(LP+予約登録)
- コンシェルジュ方式(手作業で裏側を補完)
- 有料プレβ(価格も同時検証)
- 当たり所の拡張:利用頻度×継続率×単価のいずれかが突出する面を増やす
レッドオーシャンで勝つための要点
- ニッチ化:特定業界・ロール・課題に特化(“誰の何の仕事をどれだけ速くするか”を明確化)
- 運用力差:LTV>CACが再現する販促/オンボーディング設計
- サプライ最適化:在庫/供給/サーバコストの固定費圧縮と回転率改善
指標設計(どちらでも使える)
- 獲得効率:CAC、初回購入CPO、トライアル→有料転換率
- 継続・満足:12週継続、NPS、解約理由の1位改善
- 価値検証:価格感度(PSM分析の“許容上限”推移)、プレミアム比率
- 成長の質:有料紹介率、オーガニック流入比率
よくある誤解と対処
- 「完全に新しい発明が必要」:不要。価値の組み合わせで十分。
- 「競合ゼロでなければ青ではない」:顧客の意思決定軸が変われば実質ノーコンペになる。
- 「まずは機能を全部」:非推奨。“高頻度で使う1シーン”に絞ってMVP。
使い分けの指針
- 短期売上・現金化が急務:レッドで“最も痛い課題”にニッチ特化
- 中長期の粗利・優位性を育成:ブルー仮説をERRCで設計 → LP/価格で段階検証
ミニチェックリスト(保存版)
- [ ] 非顧客の“回避理由”を10個言語化した
- [ ] 競合比較表ではなく、顧客の行動フローで課題を可視化した
- [ ] ERRCで“やめる”を先に決めた(足し算より引き算が先)
- [ ] 価格モデルを少なくとも2案でAB検証した
- [ ] KPIは継続・単価・紹介のいずれかを主軸に置いた
まとめ
- レッドは効率勝負、ブルーは価値軸の再設計。どちらも有効で、局面により併用が最適です。
- まずは小さく検証し、当たり所を数値で見極めてから投資を厚くする。これが最短距離の王道です。
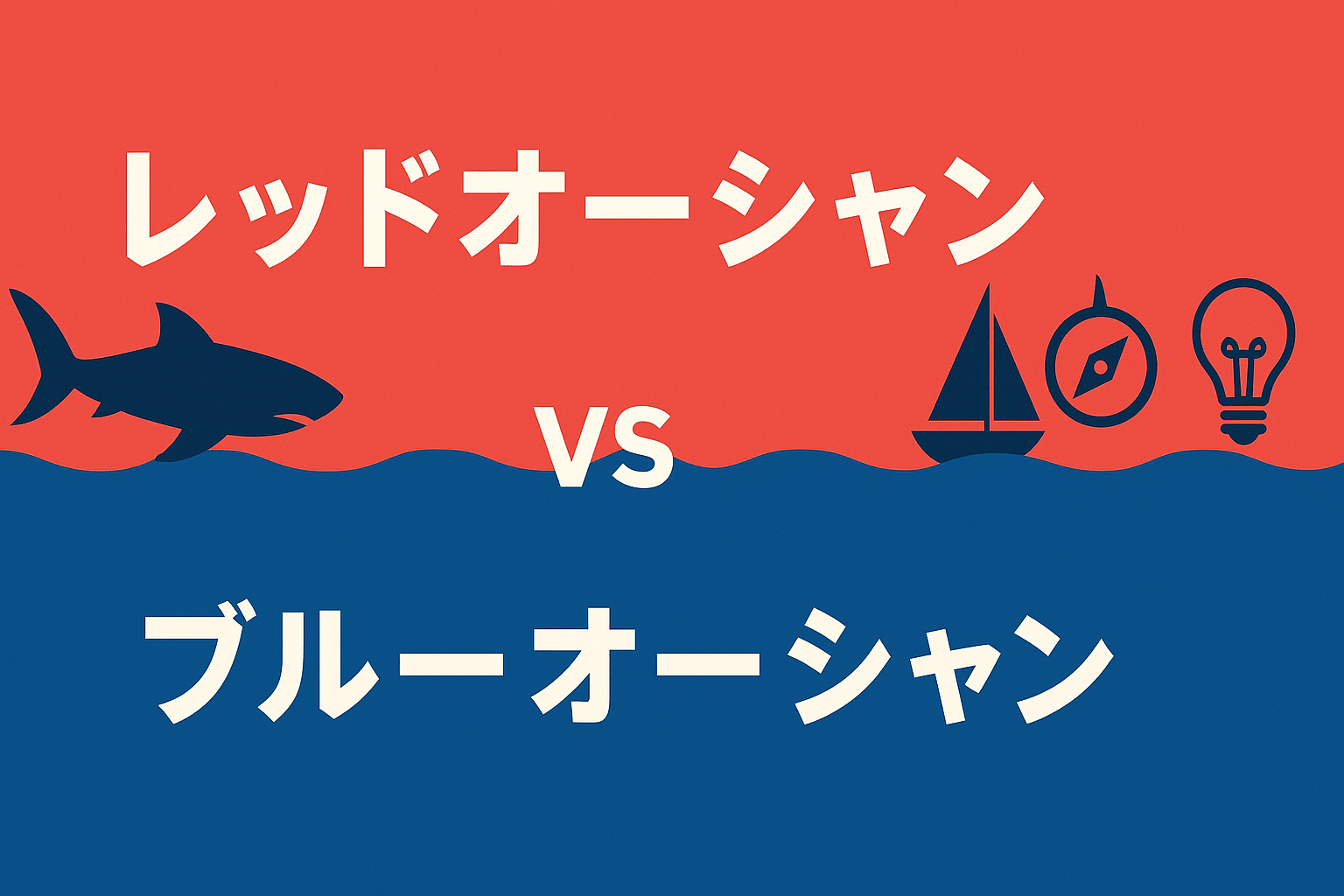


コメント